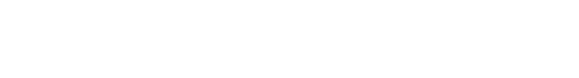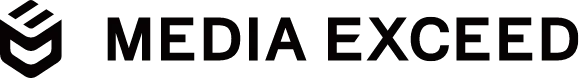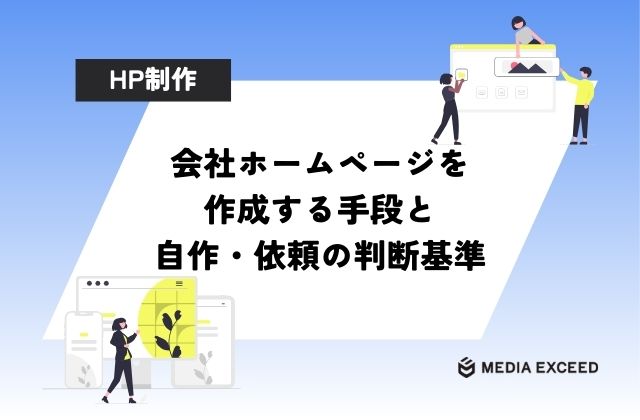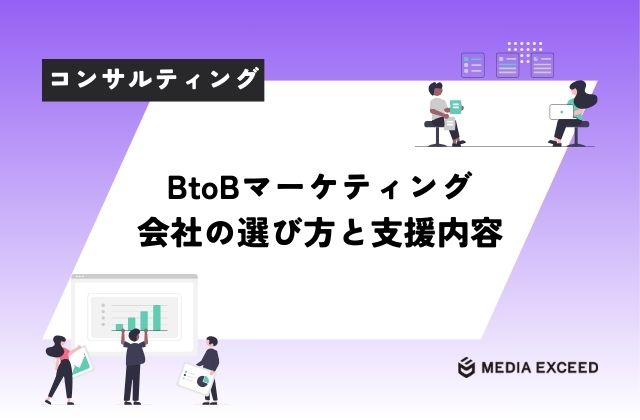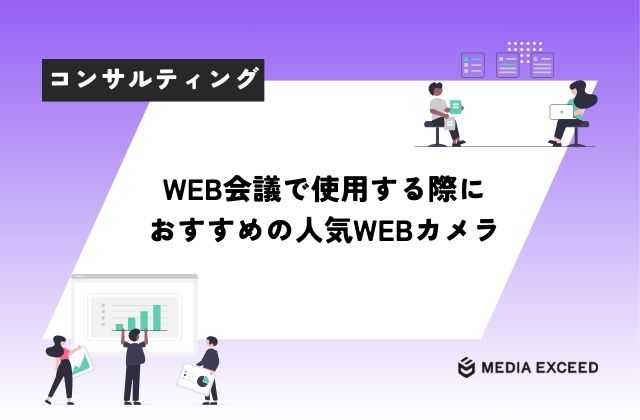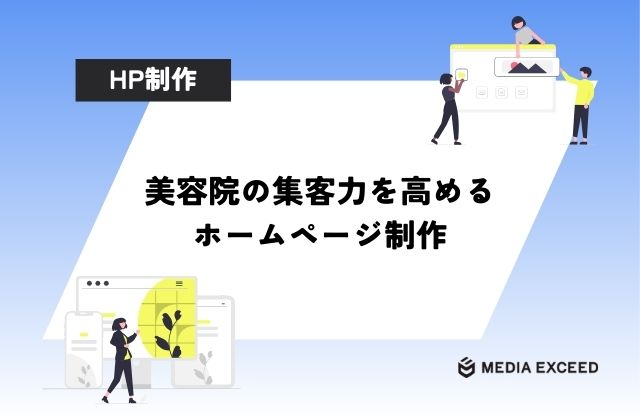「SEOはもう通用しない」「オワコンだ」といった声を耳にする機会が増えていませんか?
かつて有効だったSEOの手法が今は通用しなくなっているのは事実で、最近ではAIで記事を作成できる時代になってきています。
しかし、それはSEO自体が終わったのではなく、求められる内容や考え方が変化したことが主な要因です。
本記事では、「SEOオワコン」の背景を整理しつつ、2025年に通用する最新のSEO対策を徹底解説していきます。
株式会社メディアエクシードでは、従来のSEO施策から、最新のAIにも対応したSEOをご提案!
サイト制作からコンテンツ施策、広告運用、SNSマーケティングなど、Webマーケティング全般をサポートしています。
1つの会社にまとめて依頼できる分、効率的に効果を実感していただけます。
まずは下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
SEOがオワコンと言われる5つの理由

「SEOはもう通用しない」「時代遅れの手法だ」といった声を耳にすることが増えています。
実際にそう感じさせる要因はいくつか存在しており、それらが“SEOオワコン論”の背景となっています。
- オワコンの理由①:SNSや動画にユーザーが流れている
- オワコンの理由②:生成AIの台頭で検索の役割が変わってくる可能性
- オワコンの理由③:アルゴリズムの進化で従来のSEO手法が通用しなくなっている
- オワコンの理由④:短期で成果が出にくく「効果がない」と誤解されやすい
オワコンの理由①:SNSや動画にユーザーが流れている
近年、情報収集の手段としてInstagram、TikTok、YouTubeなどのSNS・動画プラットフォームが急速に存在感を増しています。
特に10〜30代の若年層を中心に、検索エンジンよりもSNSで商品やサービスを探す傾向が顕著になってきています。
こうした行動変化により、「検索の時代は終わった」と感じる人が増えているのが実情です。
しかし、後述するように、SNSはあくまで検索と並列の手段であり、代替ではありません。
検索エンジンの利用が減少したわけでも、SEOが終わったわけでもなく、現在でも重要な集客プラットフォームとして機能しています。
オワコンの理由②:生成AIの台頭で検索の役割が変わってくる可能性
ChatGPTなどの生成AIツールの登場により、ユーザーが「検索せずに情報を得る」機会が増えてきました。
これにより、従来の検索を通じたコンテンツ接触の流れが変化する兆しが見えています。
特に「要点だけを簡単に知りたい」「比較を瞬時に把握したい」といったニーズは、AIが得意とする領域です。
ただし、AIによる情報は出典が不明確なケースも多く、信頼性を補完する目的ではSEOコンテンツの価値が依然として残っています。
また、【LLMO】や【GEO】といった、AIに選ばれやすくなるサイトやコンテンツの作成のテクニックを合わせることで、SEOだけでなくAIを活用した検索から流入を見込めるようになります。
オワコンの理由③:アルゴリズムの進化で従来のSEO手法が通用しなくなっている
Googleの検索アルゴリズムは年々高度化しており、かつて有効だったSEO手法が通用しにくくなっています。
例えば、検索キーワードをタイトルや本文に多く含める、あるいは大量の外部リンクを集めるといった従来の手法は、もはや順位向上に寄与しにくいものとなっています。
現在のSEOでは、ユーザー体験や検索意図との整合性、さらにE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)といった総合的な要素が重視される傾向にあります。
このような背景により、過去の成功パターンが通用せず、「SEOではもう成果が出ない」と感じる人が増えているのが実情です。
SEOの本質が変化していることに気づかないまま旧来の方法に固執すると、むしろ評価を下げる要因となる可能性もあります。
オワコンの理由④:短期で成果が出にくく「効果がない」と誤解されやすい
SEOは中長期的な施策であり、コンテンツの作成から検索エンジンに評価されるまでに一定の時間が必要です。
一方で、広告やSNSは即効性があるため、比較すると「SEOは非効率」と感じてしまうケースもあります。
しかし、SEOは一度成果が出れば、広告費をかけずに安定した集客が可能になる「資産型の施策」です。
短期的な視点だけで評価すると、その真価が見えにくくなる点が、オワコンと誤解される背景にあります。
【SEOはオワコンではない!】今もSEOが使われ続けている理由

SNSや生成AIの台頭により、「SEOはもう効果がないのではないか」と考える方も増えてきました。
しかし結論から申し上げると、SEOは今でも有効な集客施策であり、適切な対策を行えば確実に成果へと繋がります。
SEOがオワコンと言われる理由がある一方で、現在もSEOを主要な集客チャネルとして活用している企業は多く存在します。
ここでは、現在でもSEOが現場で支持されている具体的な理由を解説します。
現在でも検索エンジンを利用するユーザーは多くいる
近年では、ChatGPTをはじめとする生成AIやチャットボットの普及により、情報収集の手段が多様化し、これらの技術は、検索エンジンに代わる新たなツールとして注目を集めています。
しかし、そのような状況下においても、「Google」や「Yahoo!」といった検索エンジンを活用して情報を調べるユーザーは依然として多数存在しています。
検索行動は、SNSのように偶然的に情報と出会う形ではなく、自ら課題意識を持って情報を探しにいく「能動的」な行為です。
「〇〇とは」「〇〇 比較」「〇〇 おすすめ」など、目的が明確な検索キーワードは、購買や問い合わせといった具体的なアクションに結びつきやすい傾向があります。
このように、情報収集の手段が増えてきた現代においても、検索エンジンはユーザーの意思決定プロセスにおける重要な出発点であり続けています。
Googleも「質の高いコンテンツ」を推奨している
Googleは近年、ユーザーにとって本当に役立つ情報を高く評価する傾向を強めています。
その代表的なものが「Helpful Content Update」や「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」と呼ばれる評価基準です。
つまり、検索順位はもはや“裏技”や“テクニック”だけで左右されるものではなく、コンテンツそのものの質と信頼性が問われる時代になっています。
SEOとは、単なる検索対策ではなく、「本当にユーザーの課題を解決できる情報提供」の戦略であり、今後もその重要性は揺らぎません。
SEO経由の流入がCVに与える影響
SEOによって獲得できるユーザーは課題意識が明確であるため、コンバージョン(CV)に結びつきやすいのが特徴です。
たとえば資料請求、サービス申し込み、問い合わせなど、具体的なアクションを伴うCVが発生しやすく、売上にも直結しやすい傾向があります。
以下は、代表的な流入チャネルのCVへの貢献度を、言語的な相対評価で整理したものです。
| 流入チャネル | CVの期待度 | 特徴 |
|---|---|---|
| SEO (自然検索) |
高い | 検索意図が明確で、購買や相談に直結しやすいです。 |
| リスティング広告 | 中程度 | 表示スピードは速いものの、費用や競合性の影響を受けやすいです。 |
| SNS流入 | 低め | 拡散力はありますが、情報収集段階のユーザーが多く、CVには至りにくい傾向があります。 |
このようにSEOは、広告に頼らずに今すぐ知りたい・買いたいというユーザーを的確に捉えられる、非常に効率的なチャネルといえます。
医療・士業・BtoBなど、検索が強い業界が多い
SEOが特に有効とされているのは、医療・士業・BtoBなど、専門性や信頼性が重視される業界です。
これらの分野では、ユーザーが慎重に情報収集を行い、正確性や実績をもとに意思決定をする傾向があります。
そのため、検索エンジンで公式サイトや専門記事にたどり着き、そこから問い合わせや申し込みに繋がるケースが多く見られます。
一過性のSNS情報よりも、論理的で客観性のあるSEOコンテンツが評価されやすいのです。
ローカル検索・MEOでの強い集客力
実店舗を持つビジネスや地域密着型サービスにおいては、ローカルSEO(MEO)が非常に強力です。
たとえば「〇〇市 歯科」「△△駅 クリーニング」のような検索では、地図表示と連動した店舗情報が上位に表示されます。
Googleビジネスプロフィールの最適化やレビュー管理を通じて、来店を促進する仕組みが構築できます。
これはSEOの一部として、現在でも多くの成果を上げている領域の1つです。
ユーザーの「買いたい/調べたい」ニーズを刈り取れる
SEOは、「今まさに情報が必要なユーザー」を捉えることに長けています。
例えば「○○ 比較」「○○ おすすめ」といった検索語句は、購入意欲が高まっている状態であることが多いです。
この段階で的確な情報を提供することで、購買や相談といったアクションに直結しやすくなります。
ユーザーの検索意図を的確に満たすコンテンツこそが、SEOの最大の強みです。
正しく設計されたSEOは今でも十分に成果を出せる
SEOで成果が出ないと感じる背景には、「設計ミス」や「目的のズレ」がある場合が多く見られます。
実際には、検索意図を正しく捉えたキーワード選定とコンテンツ設計、回遊しやすいサイト構造、明確な導線などを整備することで、今でもしっかり成果が出る手法です。
また、上位表示だけでなく、CVR(成約率)まで視野に入れた運用が行われているサイトほど、SEOの恩恵を長期的に享受しています。
SEOはオワコンな施策ではなく、従来のSEOとは活かし方が変わった施策なのです。
旧SEOと新SEOの違い

SEOは「終わった」と言われることがありますが、実際には「古いSEO」が通用しなくなっただけです。
現在では、Googleの評価軸やユーザーの行動に合わせた「新しいSEO」が求められています。
ここでは新SEOと旧SEOの違いについて比較詳しく解説していきます。
旧SEOと新SEOの違いを視覚化
最後に、旧来のSEOと最新のSEOの違いを簡単に比較表でまとめます。
| 要素 | 旧SEO | 新SEO |
|---|---|---|
| 評価軸 | キーワード密度・リンク数 | ユーザー体験・E-E-A-T |
| 施策方針 | 質より量の記事量産 | 検索意図に基づいた設計 |
| 成果の質 | 一時的なアクセス向上 | 専門性の高さ |
このように、SEOは「やり方を変えるべきフェーズ」に突入しています。
古い手法に固執せず、時代に即した戦略へ切り替えることが求められます。
旧SEOとは?かつて主流だった手法
SEOという言葉が一般化し始めた2000年代〜2010年代前半にかけては、現在とはまったく異なる考え方と手法が主流でした。
検索順位を上げるための施策は、現在では大きく異なり、ユーザー体験や情報の正確性よりも、検索エンジンに対する最適化テクニックが重視されていました。
以下では、当時の代表的なSEO手法について、3つの視点から振り返ってみます。
キーワードの詰め込み
かつてのSEOでは、狙ったキーワードをタイトル・見出し・本文などに繰り返し含めることが最も基本的かつ効果的な施策とされていました。
不自然な文章になっても、とにかくキーワードの出現回数を増やすことが検索順位の向上に直結していたため、多くのサイトでこの手法が多用されていました。
しかし現在では、Googleのアルゴリズムが進化し、文脈を理解して評価するようになったことで、こうした単純な詰め込みはむしろ逆効果と言われています。
キーワードの使用頻度よりも、その使い方が自然であるか、検索意図に即したものであるかが現在の評価基準となっています。
結果として、読者にとって読みやすく、有益な情報として成立しているかどうかが、キーワード活用の前提として求められるようになっていると言えるでしょう。
質よりも量の記事量産
以前のSEOでは、1記事ごとの内容が薄くても大量の記事を公開し、全体のページ数で評価を稼ぐ「量産型メディア」が一定の効果を上げていました。
キーワードを広く網羅し、PV数を一時的にでも増やすことで広告収益を狙う戦略が主流だった時代もあります。
しかし現在では、「Helpful Content Update」に代表されるように、Googleは記事の内容がユーザーにとって有益かどうかを最重視するようになりました。
情報の信頼性や独自性、そして筆者の経験に基づいた深みのあるコンテンツが求められており、薄い情報を数で補う手法は通用しなくなっています。
そのため、SEOにおいても「量より質」が原則となり、1記事ごとの完成度が問われる時代へと完全に移行しています。
外部リンク偏重
かつては、他サイトからの被リンク数が多ければ多いほど検索順位が上がると考えられており、質よりも数を優先したリンク集めが横行していました。
その結果、関連性の低いサイトからのリンクや、信頼性に欠ける相互リンク、購入によるリンク獲得など、不自然なリンク施策が多く行われてきました。
しかしGoogleはこうした行為をスパムとみなし、検索順位を下げたりインデックスを外したりするペナルティの対象とするようになりました。
現在では、ただリンクがあるというだけでは評価されず、リンク元サイトの信頼性や内容との関連性が非常に重要な判断基準となっています。
信頼できる情報源からの自然な引用や言及によって評価される構造が求められており、外部リンク戦略も質重視へと変化しています。
新SEOとは?今求められる3つの軸
現在のSEOでは、単に順位を上げるための“テクニック”ではなく、「ユーザーにとって有益かどうか」が最大の評価基準になっています。
Googleのアルゴリズムは進化し、コンテンツの質・ユーザー体験・信頼性といった多角的な要素をもとに順位を決定しています。
以下では、現代のSEOで重視されている3つの要素を紹介します。
ユーザー体験
現代のSEOでは検索順位の獲得に加え、ユーザーがページ内で快適に情報を取得できるかどうかが重視されています。
具体的には、ページの表示速度やモバイル端末への最適化、見やすく整ったレイアウト設計などが、検索エンジンからの評価に大きく影響します。
情報をすぐに見つけられる導線やストレスのないナビゲーション設計も、ユーザー体験の質を高める重要な要素です。
Googleはユーザーの満足度を最優先にしており、単に情報を掲載するだけでなく、ユーザーが満足する体験を提供するページを高く評価しています。
そのため、SEOでは検索にヒットするかどうかだけでなく、訪問後のページ体験まで丁寧に設計する必要があります。
E-E-A-T
E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったGoogleの評価基準です。
コンテンツの発信者がどのような経歴や実績を持っているか、どの組織に属しているかといった情報は、信頼性を判断する根拠として扱われます。
たとえば医療や金融といった領域では、筆者の資格や実務経験がSEO評価に直接影響するケースも少なくありません。
そのため、記事内に筆者のプロフィールや監修者情報、外部評価などを明記することが、検索順位を高める施策として有効です。
Googleにとって信頼できる情報源であると認識されるためには、誰が・なぜ書いているかを可視化することが重要です。
新しいSEOの施策として、記事内に筆者のプロフィールや実績を明記することも重要で、筆者を明記することでgoogleが専門性の高い記事と判断する傾向があります。
検索意図設計
近年のSEOでは、キーワードを文章中に入れるだけでは成果につながらず、その背後にある検索意図を正確に把握することが欠かせません。
ユーザーが特定のキーワードで検索する際には、「何を知りたいのか」「どんな悩みを抱えているのか」といった動機や期待があります。
たとえば「〇〇 おすすめ」と検索するユーザーは、商品やサービスの比較情報、具体的な選び方や口コミを求めているケースが多いです。
こうした意図に応じた構成や情報提示がなされているかどうかは、検索エンジンの評価にも直結するポイントです。
検索キーワードを出発点にしつつ、その背後にあるユーザー心理まで読み取ってコンテンツを設計する姿勢が求められています。
最新のSEO対策7選(2025年版)

SEOは「古い施策」と思われがちですが、毎年進化し続けています。
ここでは2025年時点で実践すべき、最新のSEO対策を7つ紹介します。
- 新SEO対策①:検索意図を捉えたコンテンツ設計
- 新SEO対策②:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化
- 新SEO対策③:内部リンクと導線の最適化
- 新SEO対策④:ユーザー体験(UX)の改善
- 新SEO対策⑤:ローカルSEO/MEOの強化
- 新SEO対策⑥:SNSや動画との連携強化
- 新SEO対策⑦:生成AIとの共存による効率的なコンテンツ制作
新SEO対策①:検索意図を捉えたコンテンツ設計
ユーザーが検索するキーワードの裏にある「目的」や「知りたいこと」を正しく理解することが重要です。
たとえば「SEOとは」と検索する人は、概要を知りたい初心者ですが、「SEO 外注 費用」と検索する人は導入を検討している段階です。
検索意図ごとにコンテンツを作り分けることで、ユーザー満足度を高め、滞在時間やCVにも好影響を与えます。
ただキーワードを含めるのではなく、意味・流れ・設計まで意識することが求められます。
新SEO対策②:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化
Googleは「誰が書いたか」「その人にどんな専門性や実績があるか」を重視しています。
前述した通り、筆者情報を明記したり、プロフィールに資格や経歴を記載することもE-E-A-T対策の一環で、新SEOに対応した強力な施策です。
サイト全体を通して、「信頼できる情報源」であるという印象を与えることが上位表示される要因となります。
新SEO対策③:内部リンクと導線の最適化
検索エンジンは、ページ単体だけでなくサイト全体の構造も評価の対象としています。
内部リンクを整備することで、クロールのしやすさや関連ページへの回遊が促され、評価の底上げに繋がります。
また、ユーザーが迷わず次のアクションを取れるよう、CTAボタンの配置やページ間導線にも配慮が必要です。
SEOとUXは切り離せない関係にあり、ユーザーの行動や購買意欲を考えながら適切に導線を作るようにしましょう。
新SEO対策④:ユーザー体験(UX)の改善
表示速度やモバイル対応、広告配置などは、ユーザー体験に大きく影響します。
特にスマホ利用者が多数を占める現在では、モバイルによく対応できている設計が不可欠です。
文字が小さい、読みにくい、遷移が複雑といった要因は直帰率を高め、SEOにも悪影響を及ぼします。
記事の内容も重要ですが、デザインの部分でユーザーに不都合がないようにユーザーを1番に考えながら作成するようにしましょう。
新SEO対策⑤:ローカルSEO/MEOの強化
実店舗を運営するビジネスでは、Googleマップやローカル検索の対策が集客に直結します。
Googleビジネスプロフィールの整備、正確な営業時間・住所の掲載、レビューへの返信などが基本対策です。
また、「地域+業種」での検索に最適化されたページを用意することも重要です。
ローカル対策は即効性と持続性を兼ね備えた施策として注目されています。
新SEO対策⑥:SNSや動画との連携強化
検索エンジン単体ではなく、SNSやYouTubeなど他チャネルとの連携による相乗効果も求められています。
たとえば、記事に動画を埋め込んだり、SNSからの流入を受ける構造を作ることで、SEO以外からも評価が得られます。
Googleは動画や画像の内容もインデックス対象としており、メディアの多様活用が今後の差別化要因になります。
新SEO対策⑦:生成AIとの共存による効率的なコンテンツ制作
ChatGPTなど生成AIは、SEOライティングを効率化するツールとして広く活用され始めています。
ただし、AIが出力する情報は信頼性や一次情報の不足といった弱点もあります。
AIの力を借りつつ、編集・監修・体験談の追加といった人の手を加えることが不可欠です。
効率と信頼性を両立させるハイブリッドな運用が今後のスタンダードとなるでしょう。
株式会社メディアエクシードでは、これらの効果的とされるSEO施策を、サイト制作・コンテンツ制作の両方の側面からサポートしています。
サイトの制作はA社へ、コンテンツ制作はB社へ…と分担する体制では、施策の一貫性が失われやすく、進行スピードの遅れや方針のズレ、最悪の場合はトラブルにつながることも少なくありません。
その点、株式会社メディアエクシードではサイト制作から保守管理、コンテンツ制作、SNS運用、広告配信までを一貫して対応可能な体制を整えています。
目的や課題に応じて最適なWeb施策をご提案・実施できるため、スムーズかつ成果につながる運用が可能です。
SEOはオワコンではないが、AI対策はするべき?

SEOは現在でも強力な集客施策の一つですが、AIの進化によって求められる内容や対策の方向性が大きく変わってきています。
今後は、AI時代に最適化されたSEO施策を実践できるかどうかが、成果を左右する鍵となります。
古いSEO施策は確かに通用しない
かつて効果的とされていたキーワードの詰め込みや被リンクの大量取得といった手法は、現在のGoogleの評価基準では逆効果となることがあります。
また、AIツールによる大量生成コンテンツが普及したことで検索エンジンも、「情報の質」や「独自性」により厳格な評価を行うようになっています。
単に文章量を増やすだけのAI生成コンテンツは、内容に一貫性がなく、読者の課題を解決できない場合、インデックスされない可能性すらあります。
これにより「昔のやり方が通じない=SEOは終わった」と誤解されることも増えましたが、実際にはGoogleの評価軸がより人間重視へと進化しているだけです。
重要なのは、過去の施策に固執するのではなく、AI時代の基準に合った方法へと切り替えることです。
評価されるSEOは変化している
現在のSEOでは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を示すことや、検索意図に沿った内容構成、ユーザー体験の最適化が重視されます。
特にAIによる情報の大量生成が可能になった今、検索エンジンは「誰が書いたのか」「どんな経験に基づいているか」といった背景を評価軸として強化しています。
そのため、AIで作成したコンテンツであっても、一次情報や筆者の体験を取り入れたり、事実確認を徹底することで評価されやすくなります。
また、情報の網羅性や独自性を担保するためには、AIを補助的に使いながら人の視点で構成や表現を調整することが欠かせません。
単なる自動生成ではなく、人が読む前提で質を担保したAI活用が今後のSEO成功のカギとなります。
新SEOで成果を出すには?
生成AIの台頭によって、コンテンツ制作のスピードは格段に上がりましたが、その一方で情報の真偽や読み手への価値提供が問われるようになっています。
そのため、AIを使って作成したコンテンツでも、筆者の体験を交えた記述や引用元の明示、読者の疑問を深く掘り下げる工夫が求められます。
さらに、著者情報の記載やサイト全体の専門性・透明性を高めることで、AI生成の信頼性に対する懸念を払拭することが可能です。
AIはSEOの脅威ではなく、適切に活用すれば、質の高いコンテンツ制作を支える強力なパートナーになり得る存在です。
SEOのこれからとAI活用のポイント

生成AIの普及により、情報の探し方や届け方は大きく変化しています。
従来の検索対策に加え、AI時代に即した新しいSEO戦略が不可欠となっています。
AI時代に求められるSEOの在り方
生成AIの進化により、検索体験は従来のリンククリック型から、AIによる要約や直接回答型へとシフトしつつあります。
この変化に対応するためのアプローチが、LLMO(Large Language Model Optimization)とGEO(Generative Engine Optimization)という新しいSEO概念です。
LLMOでは、生成AIが自社の情報を正確に理解し、回答の根拠として引用するために、論理的な構成や明確な表現、信頼できる情報ソースの提示が求められます。
また、GEOはPerplexityやYou.comなど、生成AI型検索エンジンに対応するための最適化施策であり、文脈の一貫性や最新情報の提示、引用されやすい文章構造が重要です。
どちらのアプローチも、従来のSEOとは異なり、検索エンジン以外のAIによる情報処理を前提としている点が大きな特徴です。
今後は、Google検索における順位対策だけでなく、AIに情報を「読まれ」「使われる」ことまで視野に入れたSEO戦略が必要となっていきます。
SEOに関するよくある質問

SEOを実施するにあたり、多くの方が疑問や不安を抱くポイントがあります。
ここでは、よく寄せられる質問に対して明確な回答を示していきます。
この他、「自社の場合はどうなのか」、「こういう施策は?」などの疑問点がありましたら、お気軽にメディアエクシードへお問い合わせください。
→株式会社メディアエクシードへのお問い合わせはコチラから
質問①:SEOと広告、どちらが効率的?
広告は即効性があり、短期間で成果を出したい場合に有効です。
一方、SEOは成果が出るまでに時間がかかりますが、長期的な安定集客に繋がります。
どちらか一方ではなく、目的に応じて併用するのが理想的です。
たとえば、新商品のローンチ時には広告で認知を拡大し、SEOで検索経由の流入を継続的に狙う戦略が考えられます。
質問②:SNSやAIに頼った方がいい?
SNSや生成AIの活用は非常に有効ですが、SEOとは別軸の施策です。
SNSは拡散力があり、ブランディングや話題性の創出には向いています。
一方で、検索ユーザーは情報収集や比較検討段階にあるため、意欲の高い層にリーチ可能です。
どちらかではなく、SEOとSNS・AIを組み合わせた全方位的なマーケティングが成果を最大化します。
質問③:AIで記事を作っても大丈夫?
生成AIで記事を作成することは可能ですが、そのままの使用は推奨されません。
AIは事実確認や一次情報の精度が不十分な場合があり、誤情報を含むリスクもあります。
そのため、人間による編集・監修・体験談や具体例の追加が必要です。
AIを活用する際は、補助ツールとして使用し、質の高いコンテンツに仕上げることが重要です。
質問④:成果が出るまでにどれくらい時間がかかる?
SEOの成果が見えるまでの期間は、サイトの状況や競合性によって異なります。
一般的には、施策を始めてから効果が出るまでに3〜6か月かかることが多いです。
特に新規ドメインや実績のないサイトの場合は、より時間がかかる傾向にあります。
現在行っている施策やサイトと、今後の施策内容両面からSEO施策を行い、中長期的な視点を持って、継続的に改善を積み重ねていくことが成果への近道です。
最新のSEO施策とAI対策なら株式会社メディアエクシード

SEOの在り方が変わり続ける今、成果に直結するためには本質を捉えた対策が欠かせません。
株式会社メディアエクシードは、従来の手法にとらわれず、検索エンジンとユーザー行動の変化を見据えた最新のSEOを実践しています。
時代に即したSEO戦略とAI対策で、確かな成果を
株式会社メディアエクシードは、検索順位を上げるだけでは終わらないSEOを提供できるのが大きな特徴です。
Googleの評価基準であるE-E-A-Tや検索意図の深い理解に加え、生成AI時代に対応したコンテンツ設計やAI検索対策にも取り組んでいます。
専門性と信頼性が求められるジャンルでも多数の実績があり、ローカルSEOやMEO、そしてLLMOやGEOといったAI最適化にも対応可能です。
コンテンツ制作から改善運用まで、一貫して支援
「SEOで思うような成果が出なかった」「何から手をつければよいか分からない」とお悩みの企業に対しても、メディアエクシードが戦略設計から運用改善まで一貫してサポートします。
SEO単体ではなく、広告やSNSとの連携も含めた複合的なマーケティング施策も可能で、SNSとSEOを掛け合わせることで成果を最大化していきます。
SEOが変化した今だからこそ、本質を捉えた施策が不可欠です。
【2025年版】SEOは本当にオワコン?その誤解と最新対策を徹底解説|まとめ
「SEOはオワコン」と言われることもありますが、それは古い手法が通用しなくなったという意味に過ぎません。
現在でもSEOは、正しい戦略と設計によって成果を出せる重要な集客チャネルです。
検索意図の理解やE-E-A-T、ユーザー体験の最適化が求められる中で、進化したSEOへの対応が鍵となります。
今後も変化に柔軟に対応しながら、ユーザーに価値ある情報を届ける姿勢が何よりも重要です。
目的や課題に応じて最適なWeb施策を行いたい際にはぜひ、株式会社メディアエクシードにお任せください。
関連記事
-

マーケティングコラム
会社のホームページを作成する4つの方法と自作・依頼の判断基準
2024/12/02
-

マーケティングコラム
東京のSNS運用代行会社18選!集客が上手い会社の選び方も解説
2025/02/27
-

マーケティングコラム
BtoBマーケティング代行15社|成果を出す会社の選び方と支援内容
2024/12/02
-

マーケティングコラム
SEO対策代行会社おすすめ15選と失敗しない依頼先の見極め方
2025/02/18
-

マーケティングコラム
WEB会議におすすめの高画質なWEBカメラ15選を目的別の選び方
2019/06/17
-

マーケティングコラム
美容院のホームページ制作会社10選と集客が成功するおしゃれな参考事例
2024/10/04